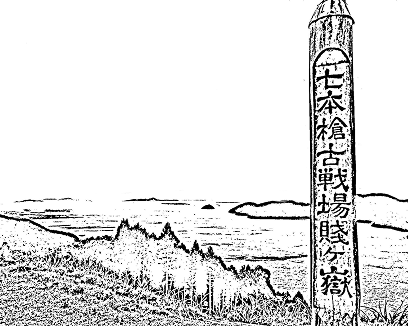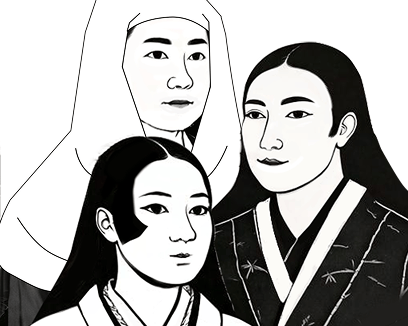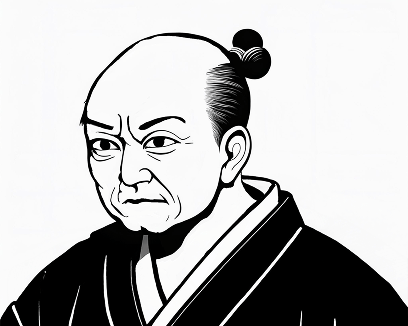秀吉の天下取りを支えるため、戦場を駆け抜け、一番槍の名誉を競い合った猛将たち。
織田信長の後継者の地位を巡り、羽柴秀吉と柴田勝家が雌雄を決した賤ヶ岳の戦いで、火花を散らし、その名を歴史に刻んだ彼らは、いかにして秀吉の信頼を勝ち得、そして時代の荒波を突き進んだのでしょうか。
のちに「賤ヶ岳七本槍」と称され、戦国の世を駆け抜けた武将たちの軌跡に迫ります。
賤ヶ岳(しずがたけ)の戦い(1583)

賤ヶ岳合戦図屏風(左隻)(長浜城歴史博物館蔵)
天正10年(1582)、本能寺の変で織田信長が倒れた後、明智光秀を討ち取り織田家中において存在感を高める羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)と、織田家の筆頭格を誇る宿将・柴田勝家の間で、信長の後継者の地位を巡る争いが始まります。
天正10年(1582)12月9日、秀吉は越前にいる勝家が降雪で出陣できない隙を突き、かつての居城であった長浜城を攻め落とします。この時、長浜城は清洲会議後に勝家が手に入れており、勝家の甥で養子の柴田勝豊が入城していました。勝豊は秀吉の軍勢を前に、すぐに降伏します。
天正11年(1583)3月、羽柴軍が、勝家と通じる岐阜の織田信孝を降し、伊勢の滝川一益を攻める中、ようやく勝家は出陣。越前と近江の境に位置する山中尾城(玄蕃尾城)に着陣します。
南下する柴田軍とそれを防ぐ羽柴軍は、余呉湖周辺で砦を築き、両軍は膠着状態となります。
こうした中、4月20日、秀吉が再び挙兵した信孝を討ちに岐阜へ進軍した隙を突き、柴田軍の佐久間盛政が、羽柴軍の中川清秀が守る大岩山砦を奇襲し、清秀を打ち取りました。
この動きを知った秀吉は、すぐ大垣から駆け戻り、佐久間隊を追撃。柴田軍は態勢を立て直すことが出来ず、勝家は居城の北庄城へ撤退しました。
この戦いが、秀吉の天下統一への大きな一歩になった「賤ヶ岳の戦い」です。
この時、秀吉の旗下で勇名を馳せた者がいます。それが、後に「賤ヶ岳七本槍(しずがたけしちほんやり)」と呼ばれるようになる7人の武将たちです。
賤ヶ岳七本槍(しちほんやり)〜賤ヶ岳の戦いで最前線を駆け抜けた若武者たち〜

賤ヶ岳の山頂は竹生島から、余呉湖まで一望できる長浜の絶景スポット。山頂広場には「賤ヶ岳七本鎗」の記念碑が建てられている
秀吉は、賤ヶ岳の戦いにおける4月21日の追撃戦で活躍した9人の小姓たちの比類なき働きを称え、感状を与えました。そして、江戸時代に入ると、この9人のうち7人が注目されていきます。それが、「賤ヶ岳七本槍」と呼ばれる7人の若武者たち(片桐且元、糟屋武則、加藤清正、加藤嘉明、脇坂安治、福島正則、平野長泰)です。
戦の最前線を駆け抜けた彼らの勇敢な槍働きが、戦況を大きく有利にし、秀吉が天下人へと羽ばたく礎となったのでした。
◾️片桐且元(かたぎり かつもと)

片桐且元 賤ヶ岳合戦図屏風より抜粋(長浜城歴史博物館蔵)
片桐且元は、弘治2年(1556)、片桐直貞の長男として生まれました。直貞は、近江国浅井郡須賀谷(現在の長浜市須賀谷町)の士族で、浅井長政に仕えていました。
天正元年(1573)、浅井氏が織田信長に滅ぼされると、浅井氏の旧領は羽柴秀吉に与えられ、秀吉は長浜城主となります。且元は弟・貞隆とともに秀吉に仕え、賤ヶ岳の戦いでは加藤嘉明らとともに先陣を切って柴田軍を突き崩しました。
文禄4年(1595)、且元は摂津茨木城主1万石の大名となります。さらに、慶長3年(1598)には小出秀政らとともに豊臣秀頼の傅役(もりやく)に任じられ、その3年後には家老となり、豊臣家を支える重鎮として活躍しました。
且元は、秀頼を補佐しつつ豊臣家存続のため、家康のもと政権運営に携わりますが、豊臣家と徳川家の関係が複雑化する中で且元の立場は揺れ動きます。
こうした状況下で、方広寺鐘銘事件が起こります。且元は徳川方との交渉に奔走しますが、秀頼、淀殿らから徳川方への裏切り者とみなされ、且元はやむなく大坂城を退去することになりました。大坂の陣では徳川方として出陣し、かつて仕えた豊臣家に敵対する立場となります。慶長20年(1615)、大坂夏の陣で豊臣家が滅亡すると、その20日後、病を患っていた且元は京都の屋敷で没しました。
◾️糟屋武則(かすや たけのり)

糟屋武則 賤ヶ岳合戦図屏風より抜粋(長浜城歴史博物館蔵)
糟屋武則は、一説によると永禄5年(1562)、播磨国加古郡(現在の兵庫県加古川市)に生まれました。
はじめは播磨三木城主であった別所長治に従っていたといわれていますが、その後、播磨へ出兵していた秀吉に仕えることになります。
賤ヶ岳の戦いでは、「七本槍」に数えられることもある桜井佐吉を助け、佐久間盛政配下の宿屋七左衛門を討ち取るという武功を立てました。秀吉から加古川郡内に2千石、河内郡内に1千石を与えられています。
その後も、秀吉の天下統一を支え続け、文禄の役(朝鮮出兵)にも出陣。三木郡の蔵入地(1万石)の代官に任じられ、文禄4年(1595)に播磨加古川城主1万2千石の大名となりました。
慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いで、武則は「七本槍」で唯一「西軍」に付いたため、戦後は改易、糟屋家は断絶しました。
◾️加藤清正(かとう きよまさ)

加藤清正 賤ヶ岳合戦図屏風より抜粋(長浜城歴史博物館蔵)
加藤清正は、永禄5年(1562)、秀吉と同郷の尾張国愛知郡中村(現在の愛知県西部)で生まれました。秀吉とは、双方の母親がいとこ同士だったという説があります。
幼少の頃から秀吉に仕え、中国攻めでは毛利方との戦いで功績を挙げます。天正8年(1580)には、播磨国神東郡で120石を与えられました。
賤ヶ岳の戦いでは、はじめ羽柴方に付くが、のちに柴田方へ寝返った山路正国を討ち取ったと伝わります。
その後、小牧長久手の戦いや九州攻めで活躍し、肥後半国19万5千石を与えられて熊本城主となりました。
朝鮮出兵(文禄・慶長の役)では槍で虎を退治して秀吉に献上したという逸話も残っており、秀吉の側近として武勇を誇ったことが伺えます。
関ヶ原の戦いでは、加藤は徳川方に味方し、戦後には球磨・天草郡(現在の熊本県南部・南西部)を除く肥後一国54万石を領有。慶長12年(1607)には堅牢な石垣、三重六階の天守を有する熊本城を完成させました。
慶長16年(1611)、清正は豊臣秀頼を説得して二条城で徳川家康との会見を導き、豊臣家の存続に尽力します。しかし、その帰途に船上で病に倒れ、帰国後間もなく病没しました。
◾️加藤嘉明(かとう よしあき)

加藤嘉明 賤ヶ岳合戦図屏風より抜粋(長浜城歴史博物館蔵)
加藤嘉明は、永禄6年(1563)、三河国幡豆郡永良郷(現在の愛知県西尾市)に生まれました。
少年の時に、父とともに長浜城主であった秀吉に仕え、秀吉の養子・秀勝に付属してきましたが、天正4年(1576)の播磨征伐を機に秀吉の直臣となっています。
賤ヶ岳の戦いでは先陣を争い、平野権平、片桐且元らとともに敵を切り崩したといいます。その後、水軍の将として各地の戦いで武功を重ね、文禄4年(1595)、伊予松前城主として6万石を領しました。
秀吉の死後、徳川家康に接近すると、関ヶ原の戦いでは東軍に属し活躍します。その戦功により20万石の大名となった嘉明は、慶長7年(1602)、松山平野の中央に位置する勝山(現在の松山市勝山町)に新たな城の築城を開始しました。
その翌年、これまで「勝山」と呼ばれていたこの地を「松山」と改め、松山城築城とともに城下町の整備を進めました。その後、会津に転封、40万石の大名として若松城を改修し、江戸にて病没しました。
◾️脇坂安治(わきさか やすはる)

脇坂安治 賤ヶ岳合戦図屏風より抜粋(長浜城歴史博物館蔵)
脇坂安治は、天文23年(1554)、近江国浅井郡脇坂村(現在の滋賀県長浜市小谷丁野町)に生まれました。
永禄12年(1569)、明智光秀に属して丹波黒岩城攻めに参戦し、同年、秀吉と出会い仕えるようになったといわれています。
賤ヶ岳の戦いでは、柴田勝政の軍勢を打ち破ったことで名を馳せるようになり、この功績により山城国内で3千石を拝領しました。
小牧・長久手の戦いでは伊賀上野城攻めで成功を挙げ、天正13年(1585)10月に淡路洲本城主となり、3万石を与えられます。その後、洲本城主として24年間在任し、現在見られる洲本城を石垣造りの近世城郭として整備しました。
また水軍の将として、九州攻め、小田原攻め、文禄・慶長の役(朝鮮出兵)に参戦し、活躍しました。
関ヶ原の戦いでは当初は三成を中心とする西軍に属しましたが、開戦途中に家康率いる東軍に寝返り、佐和山城攻撃に加わり、東軍に貢献しました。
この功により所領を安堵され、慶長14年(1609年)に伊予大洲城主となり、5万3千石の大名として存続します。元和元年(1615年)家督を子の安元に譲り、自身は隠居して京都西洞院に住み、寛永3年(1626)に没しました。
◾️福島正則(ふくしま まさのり)

福島正則 賤ヶ岳合戦図屏風より抜粋(長浜城歴史博物館蔵)
福島正則は、永禄4年(1561)、尾張国海東郡(現在の愛知県あま市)に生まれ、幼少より秀吉に仕えました。賤ヶ岳の戦いでは一番槍のうえ一番首を取るという殊勲をあげ、秀吉から別格の恩賞5千石が与えられました。
文禄4年(1595)、尾張清洲城主となり、2千万石を与えられ、豊臣家の重臣として活躍しました。
秀吉の没後は、豊臣家の内部抗争が激化する中で、石田三成と対立を深めました。慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いでは徳川家康につき、東軍勝利に貢献しました。
戦後、毛利輝元が防長二か国(周防・長門)に減封されると、安芸・備後二か国の49万8000石を拝領し、広島城主となりました。
また、紀州攻めの功では11万石を与えられ、伊予今治城主となり、小田原攻めでは先手として伊豆韮山城攻撃に加わりました。
広島藩初代藩主として領国支配を進めましたが、広島城の無断改修により改易され、その後は信濃で隠居生活を送り、寛永元年(1624)に没しました。
◾️平野長泰(ひらの ながやす)

平野長泰 賤ヶ岳合戦図屏風より抜粋(長浜城歴史博物館蔵)
平野長泰は、永禄2年(1559)、尾張国津島(現在の愛知県津島市)に生まれました。天正7年(1579)、21歳の時に羽柴秀吉に仕えます。
賤ヶ岳の戦いでは、片桐且元、加藤嘉明らと柴田軍を撃破し、その戦功により3千石を拝領しました。
さらに文禄4年(1595)、秀吉から賤ヶ岳合戦の功績を再評価され、大和国十市郡(現在の奈良県田原本町)に田原本村など5千石を加増されました。
京都伏見に屋敷を構え、田原本領を統治していた長泰は、茶、和歌、能楽にも造詣が深く、細川家や公家の船橋家とも親交があった記録が残っています。このように長泰は、武将としてだけでなく、文化人としての側面も持ち合わせていたといわれています。
関ヶ原の戦いでは徳川家康方に付き、大坂の陣では、江戸城留守居を務めました。家康が駿府に隠居すると、駿府城下の安西(現在の静岡市葵区安西)に屋敷を与えられて晩年を過ごし、寛永5年(1628)にこの地で没しました。
戦いの痕跡が残る賤ヶ岳

「賤ヶ岳七本槍」の碑(賤ヶ岳山頂)
「賤ヶ岳の七本槍」が活躍した「賤ヶ岳の戦い」の舞台である賤ヶ岳山頂には戦跡碑や戦没者慰霊碑が建てられている。
賤ヶ岳七本槍の名は長浜の地に深く刻まれ、その武勇と忠義の物語は、今もなお人々を魅了し続けている。